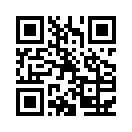14日付サンデー山口山口版の「稜線」に掲載したコラム(の若干改訂版)。
日商(日本商工会議所)の情報誌「石垣」9月号に、教育学者・齋藤孝さんへのインタビュー記事が掲載されている。

「国語力やコミュニケーション力が、社会生活を送る上で大きな意味を持つ」とし、新聞の購読についても、次のように説いている。


「昔から日本人の知的レベルが高かったのは、各家庭に新聞が毎日届けられていたから。
富裕層だけでなく一般の人々がどの国よりも新聞を読んでいたことが、平均的な国語力の高さと全国的な情報共有につながっていた。
『ネットで新聞記事を読めば同じ』だという意見には賛同できない。
毎朝届くものだからこそ、斜め読みであっても全体に目を通すわけで、自分から情報を取りにいくネットでは、一部分しか見なかったり、見るのを忘れていったりする。
さらに購読者が激減すると、世界に誇る宅配制度が崩壊するかもしれない。
そうなると販売部数が減り、ジャーナリズムが弱体化してしまう。
新聞社の取材能力が落ちれば、民主主義そのものが危うくなる。
このことについて、国民はもっと危機感を持つべきでは」
いろんな意味でのわが国の「危うさ」について異論のある人は少ないだろう。
新聞を軽んじる風潮とそのことは、無縁ではないように思われる。
「新聞購読者の増加が『国の礎』を築く」とは、言い過ぎだろうか。
日商(日本商工会議所)の情報誌「石垣」9月号に、教育学者・齋藤孝さんへのインタビュー記事が掲載されている。

「国語力やコミュニケーション力が、社会生活を送る上で大きな意味を持つ」とし、新聞の購読についても、次のように説いている。


「昔から日本人の知的レベルが高かったのは、各家庭に新聞が毎日届けられていたから。
富裕層だけでなく一般の人々がどの国よりも新聞を読んでいたことが、平均的な国語力の高さと全国的な情報共有につながっていた。
『ネットで新聞記事を読めば同じ』だという意見には賛同できない。
毎朝届くものだからこそ、斜め読みであっても全体に目を通すわけで、自分から情報を取りにいくネットでは、一部分しか見なかったり、見るのを忘れていったりする。
さらに購読者が激減すると、世界に誇る宅配制度が崩壊するかもしれない。
そうなると販売部数が減り、ジャーナリズムが弱体化してしまう。
新聞社の取材能力が落ちれば、民主主義そのものが危うくなる。
このことについて、国民はもっと危機感を持つべきでは」
いろんな意味でのわが国の「危うさ」について異論のある人は少ないだろう。
新聞を軽んじる風潮とそのことは、無縁ではないように思われる。
「新聞購読者の増加が『国の礎』を築く」とは、言い過ぎだろうか。