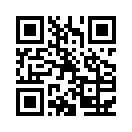28日夜、湯田温泉の「ホテルかめ福」で「福田礼輔氏『札の辻』出版記念祝賀会」が開催。

企画・運営には、「山口市菜香亭」館長でもある福田さんに、日ごろからお世話になっている有志が当たりました。
わたしもスタッフの一人として、事前準備や当日のお手伝い。
この本は、この記事でも書いたように、2000年1月から「サンデー山口」に鱧(れい)のペンネームで福田礼輔さんが連載中の「札の辻・21」を再編成し、文藝春秋社から「札の辻『鱧』の山口春秋」として、全国出版されたものです。
この会には、約130人がお祝いに駆けつけました。
まず、発起人代表の渡辺純忠山口市長があいさつ。

次に、直木賞作家・古川薫さんが「これは書誌学の材料たり得る『山口エンサイクロペディア』ともいうべき重い本」とのお祝いメッセージです。

続いて、古くからの友人でもある島田明山口県議会議長が「山口県の魅力を発信した“山口の全国大使”でもある」との祝辞を寄せられました。

また、元NHK会長・海老沢勝二さん、作家・内舘牧子さん、元自衛隊統幕長・寺島泰三さん、文芸春秋社・彭(ほう)理恵さんからのメッセージも読み上げられました。

↑ 礼輔さんへの花束贈呈は、福田百合子さん

↑ 奥様・洋子さんへは古川綾子さん
それらを受け福田さんは、出版にいたるまでのエピソードや「週に1度の連載はたいへんだが、今後も『山口の良さ』『山口が好きだ』ということを書き続けていきたい」との謝辞を述べられました。

そして、中野勉山口商工会議所会頭による乾杯の音頭で、パーティーはスタート。
着席形式にもかかわらず、あちこちで歓談の輪ができるなど、終始和やかな雰囲気でした。

最後は、岩城精二山口市教育長による万歳三唱で締めくくり。

スタッフだったからというわけではありませんが、なかなか良いパーティーだったように感じました。

↑ 当日、我が社から出したお祝いスタンド花
地図はこちら
企画・運営には、「山口市菜香亭」館長でもある福田さんに、日ごろからお世話になっている有志が当たりました。
わたしもスタッフの一人として、事前準備や当日のお手伝い。
この本は、この記事でも書いたように、2000年1月から「サンデー山口」に鱧(れい)のペンネームで福田礼輔さんが連載中の「札の辻・21」を再編成し、文藝春秋社から「札の辻『鱧』の山口春秋」として、全国出版されたものです。
この会には、約130人がお祝いに駆けつけました。
まず、発起人代表の渡辺純忠山口市長があいさつ。
次に、直木賞作家・古川薫さんが「これは書誌学の材料たり得る『山口エンサイクロペディア』ともいうべき重い本」とのお祝いメッセージです。
続いて、古くからの友人でもある島田明山口県議会議長が「山口県の魅力を発信した“山口の全国大使”でもある」との祝辞を寄せられました。
また、元NHK会長・海老沢勝二さん、作家・内舘牧子さん、元自衛隊統幕長・寺島泰三さん、文芸春秋社・彭(ほう)理恵さんからのメッセージも読み上げられました。
↑ 礼輔さんへの花束贈呈は、福田百合子さん
↑ 奥様・洋子さんへは古川綾子さん
それらを受け福田さんは、出版にいたるまでのエピソードや「週に1度の連載はたいへんだが、今後も『山口の良さ』『山口が好きだ』ということを書き続けていきたい」との謝辞を述べられました。
そして、中野勉山口商工会議所会頭による乾杯の音頭で、パーティーはスタート。
着席形式にもかかわらず、あちこちで歓談の輪ができるなど、終始和やかな雰囲気でした。
最後は、岩城精二山口市教育長による万歳三唱で締めくくり。
スタッフだったからというわけではありませんが、なかなか良いパーティーだったように感じました。
↑ 当日、我が社から出したお祝いスタンド花
地図はこちら
ここのところ、全くブログに触ることもできないような多忙な日々が続いてました。
1週間以上も記事投稿の間隔を開けたのは、初めてのことだと思います
本日も、会社で1人で仕事中です。

さて、先日は下関の「春帆楼」に、とある会合で久しぶりに行きました。
出されたフクの写真です。
地図はこちら
1週間以上も記事投稿の間隔を開けたのは、初めてのことだと思います

本日も、会社で1人で仕事中です。

さて、先日は下関の「春帆楼」に、とある会合で久しぶりに行きました。
出されたフクの写真です。
地図はこちら
きょう、サンデー山口山口版の「稜線」に掲載したコラム。

今、クリス・アンダーソン著の「FREE(フリー)」が、16万部のベストセラーになっている。
「〈無料〉からお金を生みだす新戦略」との副題が付けられたこの書籍は、今やいたるところで見かける「無料ビジネス」の4モデルを、わかりやすく解説。
また、この本自体、発売前にネット上で全文無料公開(2009年11月)したにもかかわらず、有料(1800円)の書籍もヒットしたことで、「その内容を裏付けた」との大きな反響も呼んだ。
さて、無料の地域情報紙である「サンデー山口」も「無料ビジネス」の一つだ。
同書では「三者間市場」と名付けられたビジネスモデルに分類される。
消費者は無料でさまざまなコンテンツを得るが、そのコストは「第三者」の広告主が負担。
ただし、広告費用はサービスや商品代金に含まれるので、最終的には消費者が支払っている。
逆の言い方をすれば、広告主のサービス・商品を読者=消費者が利用しなければ、媒体発行費用の負担者もいなくなり、「札の辻・21」「山口周辺」「おんなの目」や各種記事等のコンテンツも、無料で得ることができなくなるのだ。
そうならないためにも、本紙愛読者のみなさまには、広告掲載企業の積極的なご利用をお願いします。
一般生活者のみなさまは普段特別意識することはないと思いますが、公共放送のNHKを除く各種メディアは、通常、広告が大きな収入源。
フリーペーパーとなると、なおさらです。
それだけに、媒体の作り手側からすると、記事以上に掲載広告内容の利用され具合が気になります。
そこでこのコラムでは、「記事は読むけど、広告は目を通す程度」という読者の方々に、若干「警鐘」を鳴らせていただいた次第。
また、以前にも書きましたが、この「それっcha!」の運営資金も、オフィシャルブログやバナー広告だけでは足りず、当社の発行する「サンデー山口」「HABAHABA」の広告費から充当しております。
それ故「それっcha!」ユーザーの皆様方には、「サンデー山口」および「HABAHABA」だけは、他の媒体とは区別して“特別な愛情”を持って接していただけると、うれしいです。
今、クリス・アンダーソン著の「FREE(フリー)」が、16万部のベストセラーになっている。
「〈無料〉からお金を生みだす新戦略」との副題が付けられたこの書籍は、今やいたるところで見かける「無料ビジネス」の4モデルを、わかりやすく解説。
また、この本自体、発売前にネット上で全文無料公開(2009年11月)したにもかかわらず、有料(1800円)の書籍もヒットしたことで、「その内容を裏付けた」との大きな反響も呼んだ。
さて、無料の地域情報紙である「サンデー山口」も「無料ビジネス」の一つだ。
同書では「三者間市場」と名付けられたビジネスモデルに分類される。
消費者は無料でさまざまなコンテンツを得るが、そのコストは「第三者」の広告主が負担。
ただし、広告費用はサービスや商品代金に含まれるので、最終的には消費者が支払っている。
逆の言い方をすれば、広告主のサービス・商品を読者=消費者が利用しなければ、媒体発行費用の負担者もいなくなり、「札の辻・21」「山口周辺」「おんなの目」や各種記事等のコンテンツも、無料で得ることができなくなるのだ。
そうならないためにも、本紙愛読者のみなさまには、広告掲載企業の積極的なご利用をお願いします。
一般生活者のみなさまは普段特別意識することはないと思いますが、公共放送のNHKを除く各種メディアは、通常、広告が大きな収入源。
フリーペーパーとなると、なおさらです。
それだけに、媒体の作り手側からすると、記事以上に掲載広告内容の利用され具合が気になります。
そこでこのコラムでは、「記事は読むけど、広告は目を通す程度」という読者の方々に、若干「警鐘」を鳴らせていただいた次第。
また、以前にも書きましたが、この「それっcha!」の運営資金も、オフィシャルブログやバナー広告だけでは足りず、当社の発行する「サンデー山口」「HABAHABA」の広告費から充当しております。
それ故「それっcha!」ユーザーの皆様方には、「サンデー山口」および「HABAHABA」だけは、他の媒体とは区別して“特別な愛情”を持って接していただけると、うれしいです。
日々慌ただしく、ブログに書きたくともアップできないままになっているネタが、山のようにあります
今回の“お蔵出し”は、2月にどういうわけか2度も訪れた、尾道で食べた本場の「尾道ラーメン」。
そして2回とも行ったのは、地元の人に教えてもらった中で開いていた「尾道ラーメン 壱番館」。
こちらのお店、もともと通販専門だったのに「ラーメン店と変わらない」との評判が高まり、「それなら」と、実店舗を構えられた変わり種です。
一番人気は「尾道角煮ラーメン」とのことで、初回はそれを注文。



↑ オーソドックスな「尾道ラーメン」はこれです。

↑ 店内には、尾道ラーメンに関する説明板も
初回で“傾向”をつかんだ2回目のオーダーは「尾道チャーシューラーメン」に「味玉」をトッピング。

ここのチャーシューはめちゃウマなんです!
地図はこちら

今回の“お蔵出し”は、2月にどういうわけか2度も訪れた、尾道で食べた本場の「尾道ラーメン」。
そして2回とも行ったのは、地元の人に教えてもらった中で開いていた「尾道ラーメン 壱番館」。
こちらのお店、もともと通販専門だったのに「ラーメン店と変わらない」との評判が高まり、「それなら」と、実店舗を構えられた変わり種です。
一番人気は「尾道角煮ラーメン」とのことで、初回はそれを注文。
↑ オーソドックスな「尾道ラーメン」はこれです。
↑ 店内には、尾道ラーメンに関する説明板も
初回で“傾向”をつかんだ2回目のオーダーは「尾道チャーシューラーメン」に「味玉」をトッピング。

ここのチャーシューはめちゃウマなんです!

地図はこちら
15日にあった「JCイレブン会」の幹事はわたしでした。
※「JCイレブン会」についてはこちら
そしてわたしの幹事の際には、毎回同じ店でやるように、先輩方から指定されます。
そのお店は、天麩羅の「三幸」。

目の前で揚げられ、すぐに熱々をいただく。
たまりません~♪


シメは、お決まりの天丼で!

地図はこちら
※「JCイレブン会」についてはこちら
そしてわたしの幹事の際には、毎回同じ店でやるように、先輩方から指定されます。
そのお店は、天麩羅の「三幸」。

目の前で揚げられ、すぐに熱々をいただく。
たまりません~♪


シメは、お決まりの天丼で!

地図はこちら
車両撮影のために線路内に立ち入り、列車を遅延させるなどの「撮り鉄」の暴走が話題になる中、13日のダイヤ改正で廃止になる急行能登のラウンジカーのソファで横になり熟睡する「寝鉄」の存在も明らかになり、一部で「マナー違反」との話題になりました。
先日、東京で山手線に乗車したところ、なんとそんな「寝鉄」に遭遇

日曜の午前10時半くらいでしたが、時折寝返りを打ちながらの熟睡でした。
なんとも…。
先日、東京で山手線に乗車したところ、なんとそんな「寝鉄」に遭遇


日曜の午前10時半くらいでしたが、時折寝返りを打ちながらの熟睡でした。
なんとも…。
起床時には降ってなかったのに、朝のもろもろ準備中に降り出して、みるみるうちに積もり…。
今日の大雪には驚きました。
3月も、もう10日だというのに
屋根付きPからクルマを出し、1時間半ほど屋外に駐車したら、こんなに積もりました。

移動時も道路は渋滞で、車窓からはこんな風景が。

↑ 停車中の撮影です。念のため
今日の大雪には驚きました。
3月も、もう10日だというのに

屋根付きPからクルマを出し、1時間半ほど屋外に駐車したら、こんなに積もりました。

移動時も道路は渋滞で、車窓からはこんな風景が。

↑ 停車中の撮影です。念のため
「サンデー山口 山口版」で、2000年1月9日から現在まで連載が続いている人気随筆「札の辻・21」が、本になりました。
作者の鱧(れい)こと福田礼輔さんが、2009年までの201本をよりすぐった「札の辻『鱧』の山口春秋」(四六判、269ページ、税込み1500円)が、文藝春秋から全国出版です!
福田さんは周南市八代のご出身で、元山口放送専務取締役・報道制作本部長。
現在は「山口市菜香亭」の館長とともに、株式会社サンデー山口の取締役相談役を務めていただいてます。
わたしの父で初代社長である開作惇(故人)とは、昭和30年代に下関の水産記者クラブでともに切磋琢磨した親友でもあり、1978(昭和53)年のサンデー山口創刊以来、折に触れて寄稿していただいてます。
なかでも毎週の随筆連載は、なんと1000回も続いた「やまぐち菜時記」(1980年10月14日~1999年10月31日)から数えると、30年間もの長きにわたっています。
コーナー名の「札の辻」とは、昔、その地域を治めた藩政府が住民に対して条例制定や祭事、あるいは治安事項などを周知させる告知板のあった場所のことで、城下町の人通りの多い辻などに置かれました。
江戸では現在の三田通り札の辻交差点、京都では一条室山の辻、山口市では大市と竪小路の交差する辺りだったそうです。
「県内に“こぼれる”話題を、告知板のように発信できたら」との思いから、このタイトルになりました。
この本は、「やまぐち菜時記」(1983年12月)「続・やまぐち菜時記」(1987年6月)に続く、福田さんの3冊目の著書になります。
直木賞作家・古川薫さんは「福田さんは前にも『サンデー山口』に連載した『やまぐち菜時記』を出しておられるが、こんどの『札の辻』は、いちだんとバラエティーにとんだ内容になり、われわれの知的好奇心を刺激するものに仕上がった。郷土食鑑(かがみ)というべき食べ物のこと、趣味のこと、その他歴史、文学、自然科学、哲学、宗教に関わる話題に事欠かない。緩急あわせて、述べきたり述べ去るといった筆の走りが快い。文人としてつちかってきた福田学歳事記の展開である」と序文を寄せられました。
また、同じく直木賞作家の重松清さん(山口高校卒)は「山口に帰りたくなった。『ふるさと』とは、豊かな四季のことである。積み重なった歴史のことである。人生の円熟味あふれる筆と、少年の面影を残したまなざしが、それを静かに伝えてくれた。ほんとうに…たまには『ふるさと』に帰りたいなぁ」と、帯に推薦文を寄せていただいてます。
↑ 「サンデー山口連載…」とも入れていただきました

山口県に関する本といえば、これまで維新・歴史や政治ものがほとんど。
でも、この「札の辻」の中には、自然のすばらしさや文学風土の強さ、フクだけではない海の味覚、山の味覚等々がちりばめられ、どこにも政治はでてきません。
裏話ですが、文藝春秋の方は「山口とはこんなにいいところなのですか?」と、驚かれたそうです。
山口の数々の魅力が、このような形で書籍になって全国へと発信。
うれしいことです。
ちなみに、この6日・7日に上京する機会があったので、新宿の紀伊國屋書店で探してみました。
すると…

ありました!
並んでいるのは、1階の「A12 男性エッセー」コーナーです。

地元だと、文栄堂書店(本店、山口大学前店、ゆめタウン山口店)、宮脇書店コープ湯田店、フタバ図書ソフトピア山口店、明屋書店小郡店、くまざわ書店下関店、メディアステーション新下関店などで購入できます。
また、アマゾンでも購入可能です。
そして、「札の辻・21」は、毎週土曜日に「サンデー山口 山口版」に掲載。
お手元に届かない方は、こちらのホームページで読むことができます。
また、「やまぐち菜時記」「続・やまぐち菜時記」は、サンデー山口にまだ若干残部があります。
「『札の辻』と合わせて読んでみたい」と思われた方は、083-925-7912へお電話いただくか、もしくはこちらまでメールでお気軽にお問い合わせください。
↑ これはわたしの所持品なので若干汚れてますが、保管してあるのは美品です