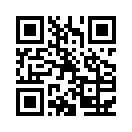7月30日付サンデー山口山口版の「稜線」に掲載したコラム。
1369(応安2)年、大内氏の24代当主弘世が、京都・八坂神社(祇園社)を勧請したのが山口・八坂神社の始まり。
そして、八坂神社の祭礼・山口祗園祭は、1459(長禄3)年に28代・教弘が京都から伝えたといわれており、約550年もの伝統を持つ。
今年も、20日の御神幸、24日の御中日祭、27日の御還幸と、さまざまな神事が繰り広げられ、幕を閉じた。
もともとは、向暑の疫病退散と、地域住民の繁栄・親睦を目的に始まった。
江戸時代初期には、15の鉾と4基の山が街を練り歩き、鷺の舞や祇園ばやしなど、その豪華絢爛な様は「西国一」と賞され、地元はもとより近隣の村々、遠くは石見の国から押しかけるほどにぎわっていたという。
しかしながら、太平洋戦争中に山鉾が廃止になり、祭り自体も2年間中断。
戦後に再開したものの、往時のにぎわいは取り戻せていない。
本家・京都や“先輩”の博多に劣るのは仕方ないにしても、小倉や戸畑など“後輩”に後れを取っている現状は歯がゆく、ぜひとも改善していきたい。
さあ、次は1週間後の「山口七夕ちょうちんまつり」だ。
8月6日(金)、7日(土)の2日間、夏の風物詩“紅ちょうちん”に、一人でも多くの市民にかかわりを持って欲しい。
以下の写真は、祗園祭御還幸の御神輿出発時。
御旅所前は、ごった返しています。


1369(応安2)年、大内氏の24代当主弘世が、京都・八坂神社(祇園社)を勧請したのが山口・八坂神社の始まり。
そして、八坂神社の祭礼・山口祗園祭は、1459(長禄3)年に28代・教弘が京都から伝えたといわれており、約550年もの伝統を持つ。
今年も、20日の御神幸、24日の御中日祭、27日の御還幸と、さまざまな神事が繰り広げられ、幕を閉じた。
もともとは、向暑の疫病退散と、地域住民の繁栄・親睦を目的に始まった。
江戸時代初期には、15の鉾と4基の山が街を練り歩き、鷺の舞や祇園ばやしなど、その豪華絢爛な様は「西国一」と賞され、地元はもとより近隣の村々、遠くは石見の国から押しかけるほどにぎわっていたという。
しかしながら、太平洋戦争中に山鉾が廃止になり、祭り自体も2年間中断。
戦後に再開したものの、往時のにぎわいは取り戻せていない。
本家・京都や“先輩”の博多に劣るのは仕方ないにしても、小倉や戸畑など“後輩”に後れを取っている現状は歯がゆく、ぜひとも改善していきたい。
さあ、次は1週間後の「山口七夕ちょうちんまつり」だ。
8月6日(金)、7日(土)の2日間、夏の風物詩“紅ちょうちん”に、一人でも多くの市民にかかわりを持って欲しい。
以下の写真は、祗園祭御還幸の御神輿出発時。
御旅所前は、ごった返しています。


きょうは、山口祗園祭の最終日・御還幸です。
1週間、御旅所に置かれていた3体の御神輿が、八坂神社へと戻ります。
わたしは、八坂神社総代として、これから御旅所へと向かいます。
午後7時から「御還幸御旅所祭」、7時半から「御還幸式・御神輿出発」、9時半から八坂神社で「御還幸本殿祭」があり、1週間にわたる祗園祭りも、ついに終了となります。
1週間、御旅所に置かれていた3体の御神輿が、八坂神社へと戻ります。
わたしは、八坂神社総代として、これから御旅所へと向かいます。
午後7時から「御還幸御旅所祭」、7時半から「御還幸式・御神輿出発」、9時半から八坂神社で「御還幸本殿祭」があり、1週間にわたる祗園祭りも、ついに終了となります。
1369(応永2)年、大内弘世が京都・八坂神社を勧請してできた由緒ある山口市の八坂神社。
先日、その総代の1人として、名を連ねさせていただくことになりました。
この八坂神社の祭礼として、1459(長禄3)年から約550年間続いているのが「山口祗園祭」。
今年は、初めて総代として参加しています。
祭りの前日・19日午後8時からは「前夜祭」。

おみこしに神様を移す「神輿遷霊祭」が執り行われました。
そして20日、午後6時より「例祭(本殿祭・浦安の舞奉納)」、「お神輿発輿祭・鷺の舞奉納」、「御神幸式」と続き、午後7時すぎに三体の御神輿が八坂神社を出発。




われわれ総代も、裃姿に提灯を持ち、市内を練り歩きました。
わたしなど、道すがらに会う知り合いの数もたかがしれてますが、ともに歩いた岸信夫参議員議員や渡辺純忠市長はさすがですね。
ちょっと歩いては話し・握手・記念撮影、またちょっと歩いては話し・握手・記念撮影の連続でした。
さて、竪小路筋は沿道の人も少なめでしたが、中心商店街アーケードに入ると大勢の人出。
3体の神輿をかつぐ約400人の裸坊と、祇園囃子を奏でる菊水鉾・真車山の山車2台が、祭り気分を大いに盛り上げてくれました。

午後9時過ぎに御神輿が「御旅所」に入り、「御神幸御旅所祭(鷺の舞・浦安の舞奉納)」が執り行われ、初日は無事終了しました。
次の出番は、総踊り「やまぐちMINAKOIのんた」もある24日(土)午後8時からの「御中日祭」と、最終日27日(火)午後7時からの「御還幸」です。
またまた、裃姿でご奉公します(^_^;)
先日、その総代の1人として、名を連ねさせていただくことになりました。
この八坂神社の祭礼として、1459(長禄3)年から約550年間続いているのが「山口祗園祭」。
今年は、初めて総代として参加しています。
祭りの前日・19日午後8時からは「前夜祭」。

おみこしに神様を移す「神輿遷霊祭」が執り行われました。
そして20日、午後6時より「例祭(本殿祭・浦安の舞奉納)」、「お神輿発輿祭・鷺の舞奉納」、「御神幸式」と続き、午後7時すぎに三体の御神輿が八坂神社を出発。




われわれ総代も、裃姿に提灯を持ち、市内を練り歩きました。
わたしなど、道すがらに会う知り合いの数もたかがしれてますが、ともに歩いた岸信夫参議員議員や渡辺純忠市長はさすがですね。
ちょっと歩いては話し・握手・記念撮影、またちょっと歩いては話し・握手・記念撮影の連続でした。
さて、竪小路筋は沿道の人も少なめでしたが、中心商店街アーケードに入ると大勢の人出。
3体の神輿をかつぐ約400人の裸坊と、祇園囃子を奏でる菊水鉾・真車山の山車2台が、祭り気分を大いに盛り上げてくれました。

午後9時過ぎに御神輿が「御旅所」に入り、「御神幸御旅所祭(鷺の舞・浦安の舞奉納)」が執り行われ、初日は無事終了しました。
次の出番は、総踊り「やまぐちMINAKOIのんた」もある24日(土)午後8時からの「御中日祭」と、最終日27日(火)午後7時からの「御還幸」です。
またまた、裃姿でご奉公します(^_^;)
きょう、サンデー山口山口版の「稜線」に掲載したコラム。
先週広島で、中国経済産業局・長尾正彦局長による「『ど真ん中』中国地域を元気発信地へ!」と題された講話を聞いた。

まず最初に、世界経済とわが国の動向を比較。
続いて、国による最近の施策等の解説がなされ、その上で「中国地域を元気にする戦略と取り組み」について、農商工連携、地域資源活用、地域発イノベーション推進、中心市街地・商業の活性化、サービス産業振興、低炭素・循環型社会の実現と環境ビジネスの育成等々、さまざまな分野について説明があった。
山口市における「元気にする取り組み」として紹介されたのは、
1.地元産農産物を用いた加工品販売の全国販売(アグリプロジェクト)
2.長期滞在者向けツアー開発(湯田温泉旅館協同組合)
3.カワラケツメイを生かした特産品づくり(徳地商工会)
4.植物工場管理技術者育成プロジェクト(山口大学)
5.中心市街地活性化基本計画(山口市)
6.商店街活性化事業計画(山口道場門前商店街振興組合)
7.新・がんばる商店街77選(山口道場門前商店街)
8.中国地域におけるハイ・サービス日本300選(てしま旅館)
9.中国地方の伝統工芸品(大内塗)
などがあった。


同様の取り組みを、もっともっと増やしていきたい。
先週広島で、中国経済産業局・長尾正彦局長による「『ど真ん中』中国地域を元気発信地へ!」と題された講話を聞いた。
まず最初に、世界経済とわが国の動向を比較。
続いて、国による最近の施策等の解説がなされ、その上で「中国地域を元気にする戦略と取り組み」について、農商工連携、地域資源活用、地域発イノベーション推進、中心市街地・商業の活性化、サービス産業振興、低炭素・循環型社会の実現と環境ビジネスの育成等々、さまざまな分野について説明があった。
山口市における「元気にする取り組み」として紹介されたのは、
1.地元産農産物を用いた加工品販売の全国販売(アグリプロジェクト)
2.長期滞在者向けツアー開発(湯田温泉旅館協同組合)
3.カワラケツメイを生かした特産品づくり(徳地商工会)
4.植物工場管理技術者育成プロジェクト(山口大学)
5.中心市街地活性化基本計画(山口市)
6.商店街活性化事業計画(山口道場門前商店街振興組合)
7.新・がんばる商店街77選(山口道場門前商店街)
8.中国地域におけるハイ・サービス日本300選(てしま旅館)
9.中国地方の伝統工芸品(大内塗)
などがあった。
同様の取り組みを、もっともっと増やしていきたい。
昨夜は、7回目となる「山口経世白虎会」が、湯田温泉の「ホテル松政」であり、参加しました。
今回の講師は、岩国市出身の世界的建築家・光井純さん。

「ボーダーレス時代の街づくり~地域が世界と直接つながる時代」の演題で、世界各地でビルの建造や街の再開発に取り組まれている経験から、各土地土地に合った都市マネジメントの必要性などを話されました。
いちいち納得できる内容でした。
今後の山口市、そして山口県の街づくりに、ぜひとも力を貸していただきたいと、心の底から思った次第です。
地図はこちら
今回の講師は、岩国市出身の世界的建築家・光井純さん。

「ボーダーレス時代の街づくり~地域が世界と直接つながる時代」の演題で、世界各地でビルの建造や街の再開発に取り組まれている経験から、各土地土地に合った都市マネジメントの必要性などを話されました。
いちいち納得できる内容でした。
今後の山口市、そして山口県の街づくりに、ぜひとも力を貸していただきたいと、心の底から思った次第です。
地図はこちら
先日の会合会場は、山口市湯田温泉の「プラザホテル寿」(山口市湯田温泉3-3-13 TEL:083-922-3800)。
同会場では立て続けに3回、会合が続きました。
複数回出席する人も何人かおり(わたしもその1人)、木村太一郎社長は毎回メニューを変えるのに腐心されたそうです。
3回目のこの日、メーンはすき焼きでした



地図はこちら
同会場では立て続けに3回、会合が続きました。
複数回出席する人も何人かおり(わたしもその1人)、木村太一郎社長は毎回メニューを変えるのに腐心されたそうです。
3回目のこの日、メーンはすき焼きでした




地図はこちら
先月のことになりますが、6月29日に「山口メセナ倶楽部」の総会があり、出席しました。
昨年度、同会は「第14回全国メセナネットワーク大会」の開催を引き受け、この記事でも取り上げたようにシンポジウムや文化公演等を実施。
本年度は引き続き、市内文化活動の支援と、景気悪化で減少を続けている会員の増強に取り組むことに決まりました。
そして閉会後、16回目となる「読売山口メセナ大賞」の授与式がありました。
今回は、結成20周年を迎えた「劇団演劇街」に贈呈。
「コミュニティーに演劇を」を活動テーマに、親子で見られる児童劇の上演などを、長く続けてきた点が評価されました。
この日は、劇(はらぺこおおかみ)のさわりの部分だけを披露していただきました。




さて、同劇団創立20周年記念の「こども演劇まつり」、7月24日(土)午後7時からと25日(日)午後2時から、山口市湯田温泉の「演劇研究所LaB21」で開かれます。
小学生以下はなんと無料!
お問い合わせは、TEL083-920-2379へ。
昨年度、同会は「第14回全国メセナネットワーク大会」の開催を引き受け、この記事でも取り上げたようにシンポジウムや文化公演等を実施。
本年度は引き続き、市内文化活動の支援と、景気悪化で減少を続けている会員の増強に取り組むことに決まりました。
そして閉会後、16回目となる「読売山口メセナ大賞」の授与式がありました。
今回は、結成20周年を迎えた「劇団演劇街」に贈呈。
「コミュニティーに演劇を」を活動テーマに、親子で見られる児童劇の上演などを、長く続けてきた点が評価されました。
この日は、劇(はらぺこおおかみ)のさわりの部分だけを披露していただきました。




さて、同劇団創立20周年記念の「こども演劇まつり」、7月24日(土)午後7時からと25日(日)午後2時から、山口市湯田温泉の「演劇研究所LaB21」で開かれます。
小学生以下はなんと無料!
お問い合わせは、TEL083-920-2379へ。
きょう、サンデー山口山口版の「稜線」に掲載したコラム。
山口県の最低賃金は、時間あたり669円。
全国平均は713円だが「できる限り早期に全国最低800円を確保、全国平均1000円を目指す」という目標が、政府の「新成長戦略」に盛り込まれた。
各種統計を見ると、国内賃金は1990年代後半から下落傾向が続いている。
先の目標は「戦略の掲げる実質2%、名目3%を上回る経済成長が前提」だとしているが、10年来続く傾向を逆転させるには、よほどの荒療治が必要だろう。
モノやサービスの価格には、製造・流通・販売時における賃金が含まれており、特にサービス業は賃金の占める割合が高い。
このままデフレ傾向が続き、モノ・サービスの値段が下がり続けるようなら、目標とは逆に、賃金は下落し続けることになるだろう。
現状の山口市を見渡すと、地場企業の賃金上昇などあり得ないことだ。
流通等のコストを規模の力で抑える“グローバル企業”による安売りおよび下請けへの値下げ圧力が、地場中小企業を「十分な賃金を払えない」体質にしてしまった。
官公庁の入札も低価格で推移し「十分な賃金を払えない」水準。
定住人口の増加も劇的には見込めず、交流人口の使うお金は流出超…。
地方の地場企業にも配慮した「戦略」であってほしい。
山口県の最低賃金は、時間あたり669円。
全国平均は713円だが「できる限り早期に全国最低800円を確保、全国平均1000円を目指す」という目標が、政府の「新成長戦略」に盛り込まれた。
各種統計を見ると、国内賃金は1990年代後半から下落傾向が続いている。
先の目標は「戦略の掲げる実質2%、名目3%を上回る経済成長が前提」だとしているが、10年来続く傾向を逆転させるには、よほどの荒療治が必要だろう。
モノやサービスの価格には、製造・流通・販売時における賃金が含まれており、特にサービス業は賃金の占める割合が高い。
このままデフレ傾向が続き、モノ・サービスの値段が下がり続けるようなら、目標とは逆に、賃金は下落し続けることになるだろう。
現状の山口市を見渡すと、地場企業の賃金上昇などあり得ないことだ。
流通等のコストを規模の力で抑える“グローバル企業”による安売りおよび下請けへの値下げ圧力が、地場中小企業を「十分な賃金を払えない」体質にしてしまった。
官公庁の入札も低価格で推移し「十分な賃金を払えない」水準。
定住人口の増加も劇的には見込めず、交流人口の使うお金は流出超…。
地方の地場企業にも配慮した「戦略」であってほしい。