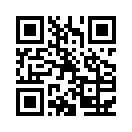5月23日付サンデー山口(山口版)の「稜線」に掲載したコラム(の完全版)。
先日、下関市豊北町方面に用事があり、クルマを走らせた。
FMラジオを聞いていたのだが、雑音が多くなったため、再サーチすると、88.9メガヘルツで止まり、スピーカーから若い女性の韓国語が流れてきた。
CMに入るときのジングルで「MBC」と聞き取れたので、後で調べてみると、釜山MBCの荒領山送信所からのFM放送だった。
標高427メートルの荒領山は、釜山広域市の南区、水営区、蓮堤区、釜山鎮区にまたがる市の中心部にあり、ドライブスポット、夜景スポットとしても人気だという。
同送信所の出力は5キロワット。
ちなみに、エフエム山口の山口送信所(大平山)の出力は1キロワットで、ここはその5倍。
とはいえ、日本でも都会だと10キロワットで流してもおり、特別に出力が大きいわけでもない。
では、なぜ普段は聞けない釜山のFM放送が聞けたのだろうか。
その原因は「Eスポ」にある。
これは、上空約100キロ付近にできる電波を反射させる特殊な電離層で、主に5月中旬から8月上旬に発生する。
この仕業によって、普段は受信できない遠方の放送が受信できる場合があるのだ。
30年ほど昔、コンポのFMラジオで、外国語のサッカー中継を受信できた時期があり、学校へ行く準備をしながら毎朝聞いていた。
放送されていた時間帯が現地では深夜に当たるため、スペインの放送局かどうかはわからないが、おそらくは1982(昭和57)年のサッカーW杯スペイン大会(6月13日~7月11日)の中継だったのだろう。
まだ日本国内では、同大会への知識も少ない時代、「なぜラジオでサッカー中継?」と疑問に思ったことを覚えている。
そして、ほどなくして受信もできなくなった。
さて、開幕まであと半月に迫ったブラジル大会。
日本代表の活躍とともに、Eスポのいたずらによって海外FM局の実況中継を受信できるかも、とちょっぴり期待している。
先日、下関市豊北町方面に用事があり、クルマを走らせた。
FMラジオを聞いていたのだが、雑音が多くなったため、再サーチすると、88.9メガヘルツで止まり、スピーカーから若い女性の韓国語が流れてきた。
CMに入るときのジングルで「MBC」と聞き取れたので、後で調べてみると、釜山MBCの荒領山送信所からのFM放送だった。
標高427メートルの荒領山は、釜山広域市の南区、水営区、蓮堤区、釜山鎮区にまたがる市の中心部にあり、ドライブスポット、夜景スポットとしても人気だという。
同送信所の出力は5キロワット。
ちなみに、エフエム山口の山口送信所(大平山)の出力は1キロワットで、ここはその5倍。
とはいえ、日本でも都会だと10キロワットで流してもおり、特別に出力が大きいわけでもない。
では、なぜ普段は聞けない釜山のFM放送が聞けたのだろうか。
その原因は「Eスポ」にある。
これは、上空約100キロ付近にできる電波を反射させる特殊な電離層で、主に5月中旬から8月上旬に発生する。
この仕業によって、普段は受信できない遠方の放送が受信できる場合があるのだ。
30年ほど昔、コンポのFMラジオで、外国語のサッカー中継を受信できた時期があり、学校へ行く準備をしながら毎朝聞いていた。
放送されていた時間帯が現地では深夜に当たるため、スペインの放送局かどうかはわからないが、おそらくは1982(昭和57)年のサッカーW杯スペイン大会(6月13日~7月11日)の中継だったのだろう。
まだ日本国内では、同大会への知識も少ない時代、「なぜラジオでサッカー中継?」と疑問に思ったことを覚えている。
そして、ほどなくして受信もできなくなった。
さて、開幕まであと半月に迫ったブラジル大会。
日本代表の活躍とともに、Eスポのいたずらによって海外FM局の実況中継を受信できるかも、とちょっぴり期待している。
5月9日付サンデー山口(山口版)の「稜線」に掲載したコラム(の完全版)。
総務省は5月4日、15歳未満の子どもの推計数(4月1日時点)は1633万人で、前年より16万人減ったと発表。
1981(昭和56)年の2760万人を境に33年連続の減少で、年齢が低くなるほど、その数も少なくなっている。
このままだと日本の人口は、今の1億2714万人が、2060(平成72)年には8674万人になる見通しだ。
65歳以上の占める割合も、25.1%から39.9%に拡大。
約1800ある地方自治体は、人口減によって2040(平成52)年に523が消滅するとも指摘されている。
そこで政府は、人口1億人程度を維持することを、初めて明確に目標に掲げるという。
2020(平成32)年ごろをめどに、高齢者に手厚い予算配分を子育て世代に移したり、女性・高齢者の労働参加の増加、地域の「集約・活性化」の進展などの対策を集中的に進める。
4月25日付の小欄でも書いたように、山口市(都市圏)の人口は、2010(平成22)年の約18万3000人が、2060(平成72)年には11万4000人に減少すると見込まれる。
このまま衰退が続くようだと「集約・活性化」によってその存在は消えてなくなるかもしれない。
その命運は、われわれ市民が握っている。
人の集まる魅力的な都市に、痛みも伴うが「変わる」のか、それとも現状維持を選び「ゆでガエル」になるか…。
総務省は5月4日、15歳未満の子どもの推計数(4月1日時点)は1633万人で、前年より16万人減ったと発表。
1981(昭和56)年の2760万人を境に33年連続の減少で、年齢が低くなるほど、その数も少なくなっている。
このままだと日本の人口は、今の1億2714万人が、2060(平成72)年には8674万人になる見通しだ。
65歳以上の占める割合も、25.1%から39.9%に拡大。
約1800ある地方自治体は、人口減によって2040(平成52)年に523が消滅するとも指摘されている。
そこで政府は、人口1億人程度を維持することを、初めて明確に目標に掲げるという。
2020(平成32)年ごろをめどに、高齢者に手厚い予算配分を子育て世代に移したり、女性・高齢者の労働参加の増加、地域の「集約・活性化」の進展などの対策を集中的に進める。
4月25日付の小欄でも書いたように、山口市(都市圏)の人口は、2010(平成22)年の約18万3000人が、2060(平成72)年には11万4000人に減少すると見込まれる。
このまま衰退が続くようだと「集約・活性化」によってその存在は消えてなくなるかもしれない。
その命運は、われわれ市民が握っている。
人の集まる魅力的な都市に、痛みも伴うが「変わる」のか、それとも現状維持を選び「ゆでガエル」になるか…。

山口県立美術館で、「大浮世絵展」が始まりましたね。
5月15日の開会式・内見会に参加しました。

↑ テープカットの様子
国際浮世絵学会創立50周年記念のこの展示、大英博物館やベルリン国立アジア美術館、ホノルル美術館など、世界中から名品が集められています。
東京であった時には、天皇・皇后両陛下も鑑賞なさったということです。
常時約160点が展示。
5月16日から7月13日までの期間中に4回の展示替えがされ、合計350点が紹介されるそうです。
内見会、音声ガイドとともに鑑賞させていただきましたが、たいへん見応えありました。
ぜひご覧ください!
4月25日付サンデー山口(山口版)の「稜線」に掲載したコラム(の完全版)。
山口商工会議所の勉強会が4月15日にあり、山口大工学部の鵤(いかるが)心治教授の講演を聴講した。
テーマは「山口市の中心市街地の活性化について」。

山口県の分散型県域構造は、
・求心性のある中心都市がない
・都市間交流と連携によるネットワーク形成が基本目標
・昭和50年代からの「県土1時間構想」
・極端な過疎地域は生まれない
・モータリゼーションの進展を促進
などの特徴を持つ。
「平成の大合併」によって各市の広域化が進展したが、一方で将来ビジョンは「コンパクトなまちづくり」を掲げるという矛盾も抱える。
また、山口市(都市圏)の人口は、2010(平22)年に約18万3千人だったのが、2060(平72)年には11万4千人に減少。
無秩序な市街化を抑制すべき「市街化調整区域」が設けられなかったために郊外開発が繰り返され、市街地は低密度に拡散。
近い将来、高齢化の進展や環境負荷軽減のためにクルマ前提の生活も成り立たなくなるが、効率的な財政投資もしづらい構造であり、妙案もない状況だという。
時代を超えて「生き残る」動物や会社などは必ず、その時代に応じて自分を「変化」させている。
山口市も「変化」を拒んでいては、未来はないと思う。
市街化調整区域を設定するくらいの大胆な施策が、今こそ必要なのではないか。
山口商工会議所の勉強会が4月15日にあり、山口大工学部の鵤(いかるが)心治教授の講演を聴講した。
テーマは「山口市の中心市街地の活性化について」。

山口県の分散型県域構造は、
・求心性のある中心都市がない
・都市間交流と連携によるネットワーク形成が基本目標
・昭和50年代からの「県土1時間構想」
・極端な過疎地域は生まれない
・モータリゼーションの進展を促進
などの特徴を持つ。
「平成の大合併」によって各市の広域化が進展したが、一方で将来ビジョンは「コンパクトなまちづくり」を掲げるという矛盾も抱える。
また、山口市(都市圏)の人口は、2010(平22)年に約18万3千人だったのが、2060(平72)年には11万4千人に減少。
無秩序な市街化を抑制すべき「市街化調整区域」が設けられなかったために郊外開発が繰り返され、市街地は低密度に拡散。
近い将来、高齢化の進展や環境負荷軽減のためにクルマ前提の生活も成り立たなくなるが、効率的な財政投資もしづらい構造であり、妙案もない状況だという。
時代を超えて「生き残る」動物や会社などは必ず、その時代に応じて自分を「変化」させている。
山口市も「変化」を拒んでいては、未来はないと思う。
市街化調整区域を設定するくらいの大胆な施策が、今こそ必要なのではないか。