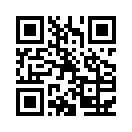2015(平成27)年5月29日付サンデー山口(山口版)の「稜線」に掲載したコラム。
山口鷺流狂言保存会は、このほど冊子「60年の歩み」を発行した。

鷺流狂言・山口鷺流の歴史、1954(昭和29)年3月6日に設立された同保存会の足跡を、多くの写真とともにたどることができる。
江戸時代、家元制度を取っていた狂言には、大蔵流、和泉流、鷺流の3流派があった。
しかしながら、幕府瓦解のあおりを受け、鷺流だけが明治維新後に衰微、途絶えてしまう。
山口鷺流は、分家・鷺伝右衛門派に学んだ長州藩お抱え狂言方・春日庄作が始祖。
彼が1886(明治19)年の野田神社上棟式で、狂言方として出演したことが、現在の山口鷺流狂言の始まりだという。
町の人々が相互に稽古をつける「伝習会」によって、鷺流は受け継がれていった。
ところが、大正期には春日の直弟子もいなくなり、急速に衰微。
それを憂えた有志が、「山口鷺流狂言保存会」を結成したのだ。
その後、1967(昭和42)年には県指定無形文化財の第1号に指定。
現在は小林栄治氏と米本文明氏が県指定無形文化財技術保持者となり、約20人の後継者を育成している。
2014(平成26)年には、「結成60周年記念公演」を含む約30公演を行うなど、その活動は活発だ。
61年目以降にも、大いに期待したい。
山口鷺流狂言保存会は、このほど冊子「60年の歩み」を発行した。

鷺流狂言・山口鷺流の歴史、1954(昭和29)年3月6日に設立された同保存会の足跡を、多くの写真とともにたどることができる。
江戸時代、家元制度を取っていた狂言には、大蔵流、和泉流、鷺流の3流派があった。
しかしながら、幕府瓦解のあおりを受け、鷺流だけが明治維新後に衰微、途絶えてしまう。
山口鷺流は、分家・鷺伝右衛門派に学んだ長州藩お抱え狂言方・春日庄作が始祖。
彼が1886(明治19)年の野田神社上棟式で、狂言方として出演したことが、現在の山口鷺流狂言の始まりだという。
町の人々が相互に稽古をつける「伝習会」によって、鷺流は受け継がれていった。
ところが、大正期には春日の直弟子もいなくなり、急速に衰微。
それを憂えた有志が、「山口鷺流狂言保存会」を結成したのだ。
その後、1967(昭和42)年には県指定無形文化財の第1号に指定。
現在は小林栄治氏と米本文明氏が県指定無形文化財技術保持者となり、約20人の後継者を育成している。
2014(平成26)年には、「結成60周年記念公演」を含む約30公演を行うなど、その活動は活発だ。
61年目以降にも、大いに期待したい。