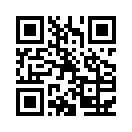きょう、サンデー山口山口版の「稜線」に掲載したコラム。
まさに、時宜に適した刊行だといえよう。
西村亘・山口県顧問(兼県立美術館長、前副知事)が、「災害から学ぶ~防災文化と危機管理」(A5判・288ページ、1500円)を、このほど出版した。
夢を「冒険学校や防災学校を設立し、子どもたちがかけがえのない命や自然を大切にしてくれること」と語る西村さんは、3月末に副知事を退任するまでの40年間、県庁生活の大半が財政もしくは災害対応だった。
特に、死者も出た2009(平成21)年県央部での「7・21豪雨災害」や昨年の県西部「7・15大雨災害」などは「語り継がなければならない」経験で、この本はそれら災害対応や人命救助に携わった経験談の講演録。
「県民への危機管理を訴えたい」というのが、出版理由だ。
いまだに関東以北では、こちらでは経験したことのないような大地震が、余震として頻繁に起き続けている。
震災後の現地の様子も日々伝わってくるが、西村さんの言う「かけがえのない命や自然」の大切さを、ひしひしと感じさせられる内容ばかりだ。
この地域にも活断層は走っている。
また、台風時期の災害は恒例行事だ。
「『想定外』『予想外』はない。泥縄ではない考え方が重要だ」との訴えを、真剣に受け止めたい。

↑ 山口県庁顧問室で著書を手にする 西村亘さん
まさに、時宜に適した刊行だといえよう。
西村亘・山口県顧問(兼県立美術館長、前副知事)が、「災害から学ぶ~防災文化と危機管理」(A5判・288ページ、1500円)を、このほど出版した。
夢を「冒険学校や防災学校を設立し、子どもたちがかけがえのない命や自然を大切にしてくれること」と語る西村さんは、3月末に副知事を退任するまでの40年間、県庁生活の大半が財政もしくは災害対応だった。
特に、死者も出た2009(平成21)年県央部での「7・21豪雨災害」や昨年の県西部「7・15大雨災害」などは「語り継がなければならない」経験で、この本はそれら災害対応や人命救助に携わった経験談の講演録。
「県民への危機管理を訴えたい」というのが、出版理由だ。
いまだに関東以北では、こちらでは経験したことのないような大地震が、余震として頻繁に起き続けている。
震災後の現地の様子も日々伝わってくるが、西村さんの言う「かけがえのない命や自然」の大切さを、ひしひしと感じさせられる内容ばかりだ。
この地域にも活断層は走っている。
また、台風時期の災害は恒例行事だ。
「『想定外』『予想外』はない。泥縄ではない考え方が重要だ」との訴えを、真剣に受け止めたい。
↑ 山口県庁顧問室で著書を手にする 西村亘さん
Posted by かいさく at 17:35│Comments(18)
│稜線
この記事へのコメント
危機管理要諦では「想定外」という言葉はありません。危機管理の基本は「悲観的に想定し、楽観的に実行せよ」です。今回の東日本大震災は、複合的危機でした。しかし、自然の驚異の甘さを実感しのです。人間の愚かさを今一度反省すべきです。特に、福島原発は、人災であり、ヒューマンエラーの典型的な事故と考えます。
Posted by 危機感アドバイザー尾下義男 at 2011年04月20日 06:22
尾下義男様、コメントありがとうございます。
プロフィル等、拝見しました。
今回の被災地における災害ストレス、想像を絶するものでしょうね。
言葉がみつかりません。
ここ山口では、震災発生後に1度も地震が起きてません。
そのこともあり、東日本で起きていることは、まるで外国での出来事のよう。
「これではいけない」と左脳で考えるのですが、右脳はどこか楽観的で、それを打ち消してしまうのです。
人間の愚かさですね…。
「悲観的に想定し、楽観的に実行せよ」、肝に銘じておきます。
Posted by 開作 真人 at 2011年04月20日 18:38
今年お世話になりました
講演テーマ 「東日本大震災の教訓 ~地域の絆~」です。
災害が起きたらまず何が一番大事か?
それは自分の身を守ることが大事です。
まず自分の身の安全を確保してから周りの人を守りましょう。
心と体が健全でなければいい仕事はできません。
健康を確保するため労働安全衛生法があります。
組織のトップは職員が心も体も健康で安心して働けるため安全配慮義務が必要です。
日頃から心と体のリカバリーが必要となります。
「ヒヤリハットの法則」といって非常に小さなミスが重なり大きな事故につながることがあります。
これを防ぐためには「5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)」、「KY(危険予知)、KYT(危険予知訓練)、KYK(危険予知活動)」が大事です。
災害とは災害対策基本法に定められたもので、局所的に、地域で処理能力を超え、他の地域からの救援を必要とする、多数の被害と被害者の発生する非常事態の事です。
「Disaster」悪い星回りなどと言われています。
災害の種類としては自然災害(広域災害)、人為的災害(局所災害)、特殊災害(NBC災害 核・生物・科学による災害=今回の原発事故、オウム真理教による地下鉄サリン事件等)が今日大きな問題となっています。
今回の東日本大震災の特徴は地震・津波・原発が同時に起こったトリプル災害であったということ。
広域性・甚大性・複合性を含んだ災害からはやくリカバリーしなければなりません。そのためにはいち早い復旧・復興が必要です。
防災とはなにか?災害を出さないことです。
しかし今回の震災においては災害を防ぐことができませんでした。これを教訓として「減災」という考え方を提唱しています。これは被害を最小化することに軸足をおき、地域にあった防災を行うことです。
視点はまず一人一人の命を守ること。「悲観的に想定し、楽観的に準備」することです。30日後に備えつつ、30年後にも備える。このことによって防災の「負のスパイラル」を断ち切ることです。
災害の及ぼす影響としては社会への影響、生活(職場)への影響、そして今回の震災ではトラウマ現象による恐怖・絶望感・無力感など、精神面への影響が精神的苦痛として国民に重くのしかかっています。
被害の拡大要因としては過去の経験による「予測の甘さ」や、偏見が正常化してしまう「自分は大丈夫という対応の甘さ」、物事に慣れてしまう「オオカミ少年効果」が挙げられます。
地震行動の中で「3.3.3の原則」というものがあります。
3分間は自分の身を守る、3時間で安全な場所に避難する、3日間で初期の避難所生活を切り抜ける、3週間3ケ月で仮設住宅へ、復興のまちづくりを目指すという原則です。
職場の防災対策における避難・誘導の留意点として「オ・カ・シ・モ」の合言葉があります。「オ:押さない、カ:駈け出さない、シ:喋らない、モ:戻らない」がとても重要な合言葉となります。
また、職場防災の基本的な考え方として1.生命の安全確保、2.二次災害の防止、3.地域貢献・地域との共生、4.事業継続が重要となってきます。
これらの対策が日頃から行われているか?これを「BCP/BCM(事業継続管理)」といいます。
職場の防災対策がツームストン・セーフティ(墓石型の安全対策)にならないようにしなければいけません。
つまり現実的な対策を行い、後の祭にならないようにしなければいけません。
災害に備えてすべきことは、住民一人ひとり、そして地域で災害に備え地域での災害犠牲者ゼロを目指すことです。
広域災害から身を守るため防災コミュニティー(地域の絆づくり)の推進が必要となります。
絆は人の和、心の和、地域の輪。相手のために何をできるのか思い続けること、人の役に立つこと、そして自分の存在価値を知ることです。
安心安全に慣れて忘災とならないように、減災へ挑戦してください。
Posted by 危機管理アドバイザー尾下義男 at 2011年12月22日 20:26
東日本大震災から一年以上が経った5月の連休に岩手、宮城、福島、茨城の被災地に足を運びました。現在なお、どの地域も復興まではほど遠く、疲弊した状態が続いている現状を目の当たりにし、目頭が熱くなりました。
「絆」という言葉が巷に氾濫していますが、この「絆」という言葉は、マスコミの造語であることが分かりました。被災者の方々にお話を伺うと、マスコミの方々が、「絆」を強調するようにと言われたそうです。つまり、マスコミ側は報道をしてあげるという「上から目線」の態度をとっているように感じました。あくまでも、「主」は、被災者の方々であり、マスコミを含め被災地に入る私達は、「従」であることを強く肝に銘じることを忘れてはならないと感じました。被災地の復興を心から願うのであるならば、真の「絆」を目指して、国民一人一人が、自分達が出来ことに真摯に向き合って頑張ることではないでしょうか。私も「減災社会」の構築のために微力ながらお手伝いをさせて頂きます。
防災講演承ります。危機管理アドバイザー尾下義男
Posted by 危機管理アドバイザー尾下義男 at 2012年05月07日 13:19
お世話になります。
平成24年11月3日東京大学駒場キャンパスで「日本精神対話学会」から研究論文推薦賞を受賞しました。「震災と心の危機管理」がタイトルで、趣旨は、「災害は」自然と社会環境との重層 的構造で起きる。東日本大震災では被災地に幾度も足を運び見聞いた「サバイバーズ・ギルト」、「死の境地」とはいかなるものか。これは、机上の空論即ち知的怠惰を廃した真実の体験報 告です。
東日本大震災は、行方不明者を含めて約二万人の尊い命が奪われた。「震災」という表現を使 うには後ろめたさを覚える。間違いなく生活基盤と生命基盤が重大な危機に直面されている。変わり果てた故郷の光景に心が傷つき、職を失い、住む場所を追われ、家を崩壊され、家族を亡くし、財産を失う、孤独死、広がりゆく放射能汚染など。「東北ガンバレ!」のメッセージだけが虚しく響いている。小職は、「減災社会の構築」に向けて微力ながら力添えしています。関係各位におかれましては、この現状を真摯に受け止めて、「上から目線」ではなく、一刻早い「見れる化」の対策が急務であることを肝に銘じていただきたい。
尾下拝
Posted by 危機管理アドバイザー尾下義男 at 2012年11月08日 08:47
前略
お世話になっています。
危機管理アドバイザー・精神対話士(いばらき防災大学講師)の尾下と申します。
東日本大震災は、過去に例を見ない未曾有のトリプル災害(地震・津波・原発)でした。その過酷の現場で、全国からボランティアの方たちは、昼夜を問わず、我が身を返り見ず、懸命に救助される姿に国民のお多くが、感謝と感銘を受けています。しかし、彼らは強い使命感と責任感を背負っているために、命救えぬ自責の念(サバイバーズ・ギルト=罪悪感)に駆られ、精神ストレス「災害ストレス」に罹り、現在は放心方状態で、生活態度が一変してしまいました。ところが、このケア体制づくりが整っていないのが現状です。今回の東日本大震災においても被災者のケア活動を行いつつ、災害ストレス対策の重要性を含む防災リテラシーを講義・講演を行っています。被災地に赴く前の研修の必要性を痛感しているところです。つきましては、貴下の研修に「被災者と支援者のケア対策」の一端をお話しさせて頂く機会をお与へ頂ければ幸甚に存じます。尾下拝
参考文献:「災害から命を守る法則= 尾下著」Hon’sペンギン
防災危機管理研究所
代表:尾下 義男
Posted by 尾下義男 at 2013年01月28日 05:19
「減災(心災)社会の構築に向けて」
東日本大震災の未曾有の災害に直面し、困難な状況と向き合った多くの人々がいました。彼らには、悲しむ時間さえありません。被災地へは何度も足を運びました。2年経った現在もなお被災地は、荒涼とした風景が広がり、「被災者の心の傷」は深く、疲弊状態が続き将来の展望が開けない「五里霧中」の状態です。「防災・減災(心災)対策」は、個人から国まで、それぞれのポディションが如何に防災行動力をアップし、さらに継続向上するかが大きな課題です。「靴を測って足を削る」のではなく「悲観的に準備(想定)し、楽観的に実施(対応)する」を基本とする減災社会の構築(build a society mitigation)が強く求められます。東日本大震災の教訓を生かした「減災社会」の構築は、抽象的机上論の知的怠惰性を脱し、防災共育(お互いに育てる環境づくり)に軸足を置き、防災リテラシー(災害から生命・財産を守るために対応力・実践力・応用力の向上を図る)を普及することが重要です。防災の敵は「忘災」を「金字塔」とし、一層鋭意努めて参る所存です。ご支援ご指名賜れば幸甚に存じます。 尾下拝
Posted by 尾下義男 at 2013年02月10日 09:02
前略
お世話になります。
危機管理アドバイザー(防災士)の尾下と申します。
現在、「防災・減災社会の構築に向けて」を主軸に講義(大学・専門学校)・講演(全国各地)活動中です。
災害サイクルに3という数字(3分・3時間・3日間)のフェーズで対策を呼び掛けていますが、南海トラフ巨大地震では、1週間分の食料や水の備蓄が必要とされています。これからの災害サイクルは7(7分・7時間・7日間)となります。一人ひとりが生き抜くために、地域で、企業で、自治体で、巨大地震と真摯に向き合い、「事前防災」を主軸に、防災対策と防災行動力の強力な推進が喫緊の課題です。
阪神・淡路大震災以後「7(自助):2(共助):1(公助)」の法則が定番でした。しかし、東日本大震災のトリプル災害や南海トラフ巨大地震のような広域災害では、基本的に「自助」を主軸に、「6:3:1」へと転換を図リ、自助と地域の共助体制を強靭にして、災害から我が家、我が地域を守ること。そのためには、普段から良好なコミュニケーションを図り、人と人との強い絆で防災協働力を身につけることが大切です。
防災・減災対策は机上の空論(原理・原則)に終始せず、予想と実践と交互に繰り返して、その都度予想の間違いを修正しながら整合性のある理解を積み重ねて、東日本大震災の教訓を学び地震への備えと最新の知見等を踏まえて、防災リテラシー(災害から生命・財産を護る対策)を具体化(見える化)して、減災社会の構築(build a society mitigation)を推進することにあります。「不意の地震に不断の用意」の関東大震災の標語は、大地震から90年経つ現在も色あせていません。「尊厳ある生を守る」には、災害を知り、地域を知り、災害を正しく恐れて、減災に取り組む人づくりの育成が重要です。安全と安心の構築は、防災教育(共育)にあります。つまり、「互教互学」の精神で、後世にしっかりと受け継いで行くことが我々に与えられた使命であることを自戒しなければなりません。私は日々研鑽を重ねより一層鋭意努めて参ります。ご指導ご鞭撻賜りますようお願い申し上げます。 尾下拝
Posted by 尾下義男 at 2013年06月02日 19:55
お世話になります。
危機管理アドバイザー尾下と申します。
「震災と心の復興」
本書は、東日本大震災被災者の行動と心理、回復への経過など被災地に足を運び現実を直視し見聞し、「サバイバーズ・ギルト=生存者の罪悪感、」、「死の境地」とはいかなるものなのかが、事実に即して書きました。1人ひとりがトラウマ(災害ストレス)への理解を深め、ストレスやトラブルと冷静に向き合い、未来を豊かに身体的にも精神的にも安全・安心して暮らすために、本書が微力でも役立てば幸甚に存じます。
著者 尾下義男より
Posted by 尾下義男 at 2013年07月31日 15:45
お世話になります。
危機管理アドバイザー(精神対話士)の尾下と申します。
「震災と心の復興〜心の危機管理への提言〜」
本書は、東日本大震災被災者の行動と心理、回復への経過など被災地に足を運び現実を直視し見聞し、「サバイバーズ・ギルト=生存者の罪悪感、」、「死の境地」とはいかなるものなのかが、事実に即して書きました。1人ひとりがトラウマ(災害ストレス)への理解を深め、ストレスやトラブルと冷静に向き合い、未来を豊かに身体的にも精神的にも安全・安心して暮らすために、本書が微力でも役立てば幸甚に存じます。
著者 尾下義男より
Posted by 尾下義男 at 2013年08月18日 06:20
著者「震災と心の復興」の内容
この本は、被災者の方々というよりも、外部からの支援やボランティアに携わる方々、復旧・復興に携わる関係者の人たち、何もできないけれど、被災者と気持ちを共有したいと思っている人たちに対して書いたものです。もちろん被災者の方々に対しても災害アフタ-ケアしても意味のあるものと思っています。
Posted by ositayosio at 2013年09月26日 06:55
前略
お世話になります。
危機管理アドバイザー尾下と申します。
「防災教育の推進」
東日本大震災は、過去からの教訓を謙虚に受け入れることを私たちに教えてくれました。災害の教訓が何世代にも亘って伝えられてきている地域もあります。それを教訓として後世に確実に伝えていくうえでも、防災教育は重要です。いわば、語り継がれてきた「暗黙知」を、誰もが共有できる「形式知」へ変換することによって、一人ひとりが自分の命に責任を持てるようにすることです。
災害などの非常時に、「想定外」を言い訳にしないで総力を挙げて危機に対処していくためには、小中学校の防災教育の充実だけでなく、社会のあらゆるレベルにおいて、リスク対応力を教育し強化する必要があります。そのためには、専門的な人材育成や高度な知識・技術研究の成果をできるだけ社会に還元するための教育プログラムの充実が必要です。今こそ、人類の最大の財産ともいえるコミュニケーション能力をフルに発揮して、情報や「学び」を共有・継承し、知恵を出し合い、災害リスクに対する思考のパラダイムを転換していく必要があるのです。
東日本大震災の教訓と最新の知見等を踏まえて、防災リテラシー(災害から生命・財産を護るための対策)を具体的に効果の上がる減災社会の構築が重要です。 尾下拝
Posted by 尾下義男 at 2013年11月29日 20:43
減災・防災における「人・もの・金」
減災・防災に関わらず、ことを動かすには、「人」・「もの」・「金」がいるといわれています。しかし、言うまでも無く一番大切なのは「人」です。適切な対応力や判断力のできる人を事前に準備しておくことが重要です。行政は「減災・防災が重要だ」として、巨額の予算を付けますが、そのほとんどは「もの」を購入したり造るための「金」であり、「人」を育てたり、「人」をつけるための「金」ではありません。また、「もの」をうまく運用する「金」でもありません。原因は、行政に総合的な防災力を向上・持続し発展させることのできる「人」が不足し、その高額の予算をうまく執行できるだけの質と量の研究者や技術者などの「人」を育ってなかったことです。「お金やエネルギーは,被災地のために準備しておくのではなく,被災地で困る人を減らすために事前に有効活用する」これが基本です。減災戦略計画の実現は、たとえトップが途中で代わろうとも一貫した考え方に立って推進する必要があります。そうでなければ、ばらばらで付け焼刃的な対策によって結局、被害軽減対策が実現しないことになってしまいます。
尾下拝
Posted by 危機管理アドバイザー尾下義男 at 2013年12月19日 11:21
お世話になります。
危機管理アドバイザー尾下と申します。
「災害の危機管理と防災体制の基本」
・危機管理の基本は、災害のメカニズムを知り(knowinghazard)、弱いところを知り(knowingvulnerability)、対策を知ること(knowingcountermeasures)です。
・防災体制の基本は自助・共助・公助。しかし、住民は自助・共助・公助は1:2:7 だと思っていますが、実際は7:2:1 で、認識のギャップと行政任せの個人が、災害対応を困難にしていると言っても過言ではありません。
一般的に、防災とは、災害の被害を未然に(完全に)防ぐための行動・施策・取り組みであり、減災とは、被害を完全に封じる(防ぐ)のではなく、被害を最小限に抑えるための行動・施策・取組です。つまり、防災とは、行政主体の公助を基本とし、堤防等の整備などのハード重視のまちづくりを行うとともに、防災訓練のような発災後の救命に取り組むものであり、住民には、行政が何とかしてくれるという意識が働きやすいのです。
一方、減災とは、自助・共助を基本に、災害や突発的事故などは完全には防げないという前提に立ち、被災した場合、被害を最小限にするための平時の対策を取り組むものであり、一つの対策に頼るのではなく、小さな対策を積み重ねて、被害の引き算を行って被害の最小化を図るソフト対策・人づくり重視のまちづくりを行うものです。
東日本大震災以後、住民は目に見える形での防災対策を望む傾向にあるため、行政としては減災に重点を置く施策が重要です。
(1) 自助
自助とは、自己の責任と判断で、自分の命は自分で守るということです。地震で亡くなるかそうでないかの分かれ目は、一人ひとりの行動にあります。耐震性を高め室内の耐震対策を図り、自分の家から火災を出さない、自分の家から死傷者を出さない事前の備えが必要です。日本電産創業者の永守重信の語録に、[一人の百歩よりも百人の一歩のほうがはるかに会社を強くする]という言葉が強く胸を打ちます。住民一人ひとりが地域の災害危険性を再認識し、各個人が災害に対する意識レベルを高め、防災力、危機管理対応力を引き上げることです。しかし、一人ひとりの個人の自助努力にも限界があります。
(2) 共助
共助とは、自分・家族だけでは対応が困難なことから、町内会、自主防災会、マンション管理に属する人々で互いに助けあいを行うことです。地域社会での防災活動の基本は、自分たちの地域は自分たちで守るという意識で行動し、協働することにあります。
しかし、近年、この地域社会のつながりが弱くなり、地域社会の活動が減少し、町内会や自主防災会の活動は、どちらかというと行政の下請け機関のように位置付けられ、主体性が少なく、形骸化しています。また、高齢化の影響もあり、地域社会の活動を担う人たちが減っており防災活動にも支障をきたすようになってきました。
共助が災害時に十分に機能するためには、地域社会の再生・活性化が必要で、そのためには、昔から地域の核であり地域社会の心の支えであった地域の寺や神社(氏神様)の行事である地蔵盆、盆踊り、御遠忌、日曜学校、法話、お祭りなどの復活を通じて、人と人、地域と地域のコミュニケーションが活性化することも重要であると考えられます。
(3) 近助
これは、自助、共助をつなぐ新しい概念です。
かつて日本の地域社会では、困った時にお互いが助け合い、相談を始め醤油・味噌を貸し借りする良き習慣とも言える向こう3軒両隣があり、極めて強い地域住民の結びつきがありました。しかし、近年隣は何をする人ぞと言われるように地域住民の付き合いは希薄な状況になってきました。しかし、共助の活動を担うのは向こう3軒両隣の住民であり、自助と共助の間を埋める「近助」が重要な役割を果たすと考えられます。顔が見える付き合いの関係による助け合いです。昔から「遠くの親戚より近くの他人」、「何かあった場合に頼りになるのはご近所さん」ということになリます。
身体が元気なうちは助けられる人から助ける人へ、守られる人から守る人へと立つ位置を替え、隣人に関心を持ち、必要な時は見返りを求めず、思いやりの心で、地域や隣人を助ける、傍観者にならない心を持つという「近助の絆」を大切です。尾下拝
Posted by 危機管理アドバイザー尾下義男 at 2013年12月29日 06:44
今年もよろしくお願い申し上げます。
防災危機管理アドバイザーの尾下と申します。
「災害の危機管理と防災体制の確立」
危機管理の基本は、災害のメカニズムを知り(knowinghazard)、弱いところを知り(knowingvulnerability)、対策を知ること(knowingcountermeasures)です。
防災体制の基本は自助・共助・公助です。しかし、住民は自助・共助・公助は1:2:7 だと思っています。実際は7:2:1 で、認識のギャップと行政任せの住人・個人が、災害対応を困難にしていると言っても過言ではありません。
一般的に、防災とは、災害の被害を未然に(完全に)防ぐための行動・施策・取り組みであり、一方、減災とは、自助・共助を基本に、災害や突発的事故などは完全には防げないという前提に立ち、被害を最小限に止めるため平時から対策に取り組み、一つの対策に頼るのではなく、小さな対策を積み重ね、「BCP(Business Continuity Plan)=事業継続計画」を、家庭に置き換えると、「FCP(Family Continuity Plan)=家族継続計画」積み重ね、訓練して、被害の最小化を図るソフト対策・人づくり重視のまちづくりを行うものです。
最近では、災害対応において「自助/共助/公助」の役割分担への理解の重要性が説かれています。災害は社会全体に影響を及ぼす事象であるために、その影響を受ける個人(企業)/地域/行政のそれぞれの役割を明確にし、お互いに補完し合う必要があります。大規模な災害であればあるほど、「国・行政が何とかしてくれるハズ」と、国民は期待しがちですが、公助にも限界があります。防災対策・災害対応においては、まず自らがその生命や財産を守るという考えが基本となっていると言えます。
かつて日本の地域社会では、困った時にお互いが助け合いの「向こう3軒両隣精神」がありました。しかし、近年「隣は何をする人ぞ」と、言われるように地域住民の付き合いは希薄な状況にあります。しかし、共助の活動を担うのは向こう3軒両隣の住民であり、自助と共助の間を埋める「近助」が重要な役割を果たすと考えられます。昔から「遠くの親戚より近くの他人」、「何かあった場合に頼りになるのはご近所さん」です。それには普段から顔の見えるお付き合いをし、身体が元気なうちは助けられる人から助ける人へ、守られる人から守る人へと立つ位置を替え、必要な時は見返りを求めず、「思いやりの心」と「オモテナシの心」で、地域や隣人を助ける、傍観者にならない心を持つことが大切です。災害時には、自助・共助・公助の3つの連携が円滑になればなるほど、災害対応力を高め、被害を最小限に抑えるとともに、早期の復旧・復興につながるものとなります。 安全・安心の社会の構築は、防災教育(共育)にあります。災害を知り、地域を知り、「災害を正しく恐れ」て、減災に取り組む人づくりの育成が重要です。つまり、「互教互学」の精神で、後世にしっかりと受け継いで行くことが我々に与えられた使命です。私は自戒し日々研鑽を重ねより一層鋭意努めて参ります。ご指導ご鞭撻賜りますようお願い申し上げます。
Posted by 危機管理アドバイザー尾下義男 at 2014年01月03日 06:22
お世話になります。
防災危機管理アドバイザーの尾下と申します。
「減災対策」は危機の多極分散にある。
防災対策は,ハード・ソフトの様々な対策を組み合わせて被害を最小化することにあります。しかし,「減災」はその明確な目標や個別の対策との関係等について,必ずしも十分な社会的合意が形成されている訳ではありません。
「減災」に向けて実効ある取組を進めるためには,行政のみならず,住民,企業,ボランティア,自治組織等の地域の様々な主体が地域の防災対策に積極的に参画,協働する取組を強化し,社会の総力をあげて地域の防災力の向上を図っていくことが必要です。
このため「自助」,「共助」の理念の明確化とともに,ボランティアの活動環境等の整備のための具体的方策,企業の事業継続計画(BCP)・家族継続計画(FCP)・地域継続計画(DCP)の策定及び改善を促進するための法的位置付けや具体的な支援措置の充実等について検討していくことが必要です。
国は、今後想定される大規模自然災害として、南海トラフの巨大地震とともに、首都直下型地震や富士山等の火山噴火が挙げられており、東京圏の中枢機能のバックアップに関する議論が進められていますが,危機管理の面からも、我が国が国として「生き延びる」ために、日本の機能の一極集中を是正し、多極分散型社会への転換を図る議論を、真剣に取り組むべきです。尾下拝
Posted by 尾下義男 at 2014年02月03日 19:40
危機管理アドバイザーの尾下です。
「防災対策は国境を超えて」
この度、中国北京の視察団(北京)に、「災害大国日本の防災・減災対策と災害ストレス」を演題に講演を行いました。日本は自助7・共助2・公助1。つまり自分の身は自分自身で守るのが基本ですが、中国は全く逆で、大変驚いていました。また、災害ストレス(セルフヘルプという概念そのものが浸透していない)そのものの存在をあまり理解できないようです。最後に、大災害は必ず来る。だが、その大災害の被害を最小化(減災)することは、日本人の知恵と強固な社会によりできる。そのために、東日本大震災の教訓を活かし、災害に強い国にする必要があると締めくくった。視察団は、大変熱心でかつ興味深く小職を中国へ招聘し、防災対策と災害ストレスについて話して欲しいとのことでした。これは、冗談だと思いますが、それに報いるためにも更なる努力を積み重ねて参りたいと存じます。小職にとっても大変有意義かつ実りある数日でした。
この度、NHK(クローズアッフ現代)で放送されたことから、「レジリエンス」について、防災危機管理の面で問い合わせを受けました。
「減災対策の危機管理とレジリエンスについて」
被災者の困難が長期に継続する今回の東日本大震災では、被災者に内在する「強み」への気づきや「希望」という視点がなければ再発のリスクを低減することは困難です。しかしながら、これまでは詳細な研究が行われていないのが現状です。たとえば、「大丈夫何とかなる」という首尾一貫感覚のSOC( Sense of Coherence)、「どん底の状態から立ち直る力」であるレジリエンス(Resilience)、それに「困難な状態からのポジティブな心理的変化」である心的外傷後成長(PTG:Post-Traumatic Growth)などを用いることで、被災者のポジティブな心理的変化を各要素に分類して詳細に分析を行うことが必要です。今回の東日本大震災の厳しい経験から、多くの方がこれから真に安全で安心できる社会を築いていかなくてはと痛切に感じています。しかし、災害に強く、安全・安心な社会とは、どのようなことを意味するのでしょうか。
私は、本当の強さとは、「困難な状況に負けないこと」であると考えています。自然の猛威を前に人間は無力ですが、東日本大震災を経験した私達が、歴史の生き証人としてこの教訓を今後に活かさないのであればそれは天災ではなく人災にもなり得ることを忘れてはいけないと自分に言い聞かせる度に、これからの真に安全で安心できる社会の構築に必要なことは、困難な状況に負けない力を備えることであると強く感じています。
困難な状況に負けない力とは、困難を乗り切る力です。大きな災害や事故に見舞われた時に、私達の組織や地域社会は、いくら入念に防災対策を講じていたとしても、程度の差こそあれ影響や被害を受けることは避けられないでしょう。しかしながら、傷を負いながらも堪え忍び、厳しく困難な時期を何とか乗り切り、乗り越える力こそが、重要になるのではないでしょうか。それが、「レジリエンスの高い」組織や地域社会の姿であると考えます。
それには、まずは日頃十分な備えをすることが基本となります。対策を講じていれば問題が生じたとしてもその程度は軽くてすむことが期待されます。被害の程度が軽微であれば、その後の復旧・復興の過程は大きく変わってくるでしょう。事前に備えることの重要性はレジリエンスを高めるために、とても大事な要素であることに変わりはありません。そのことに加えて、レジリエンス向上のためには危機管理の実質的な仕組みと仕掛けを充実していくことが大切になると思います。例えば、意志決定やコミュニケーション、地域連携、情報共有管理などがレジリエンス向上のための重要な指標となるのではないかと考え講義・講演で力説しているところです。
今後ともご支援ご指導賜りますよう宜しくお願い申し上げます。尾下拝
P・S 「プレス民主」325号に小職の「分散型危機管理」が掲載されています。
Posted by 尾下義男 at 2014年04月21日 19:35
お世話になっています。
危機管理アドバイザーの尾下と申します。
「韓国船沈没事故から学ぶ危機管理能力」
1件の重大事故の背後には29件の軽微事故があり、更に背景には300件の異常が存在するという「1:29:300の法則(ハインリッヒの法則)」があります。本来のハインリッヒの法則は、事故に至る前に多発するミス、つまり「ヒヤリ・ハット」を反省し、この対策を検討することです。
今回の韓国船沈没事故概要をテレビで毎日放送されていますが、これを「対岸の火事」とするのではなく、「靴を測って足を削る」の愚行を止めて、「悲観的に準備をして、楽観的に行動せよ」という防災・危機管理の基本に立ち返り戻り、危機管理対応能力を再構築せよとの警告でもあり真摯な反省と対応が望まれます。尾下拝
Posted by 尾下義男 at 2014年05月04日 04:26
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。