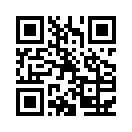7月12日付サンデー山口(山口版)の「稜線」に掲載したコラム。
ゲリラ豪雨続きの日々が一転、7月8日の梅雨明け以降は猛暑の連続だ。
昨年の梅雨明けは23日、平年は19日であり、今年の夏到来は「ぶち早い」、そして「ぶち暑い」。
さて、「山口盆地の夏」といえば、恒例の夏祭りが思い浮かぶ。
そのトップを飾るのは、大内氏28代・教弘が1459(長禄3)年に京都から伝えて以来、550年もの伝統を持つ山口祇園祭。
20日(土)の御神幸、24日(水)の御中日祭、27日(土)の御還幸を中心に、さまざまな神事が繰り広げられる。
江戸時代初期には、15の鉾と4基の山が街を練り歩き、鷺の舞や祇園ばやしなど、その豪華絢爛な様は「西国一」と賞された。
地元はもとより近隣の村々、遠くは石見の国から押しかけるほどにぎわっていたという。
しかしながら、太平洋戦争中に中断。
戦後に再開されたものの、往時のにぎわいは取り戻せていない。
今年は、御輿が街を練り歩く初日と最終日が土曜日にあたるため、例年以上のにぎわいに期待したいところだ。
サンデー山口も、盛り上げに一役買おうと、18日(木)に「山口祇園祭特集号」を特別発行。
同日の新聞折込に加えて、20日には祭り会場にてスタッフが手配りします。
ぜひご覧ください。

↑ 昨年の御神幸直前の八坂神社の様子
ゲリラ豪雨続きの日々が一転、7月8日の梅雨明け以降は猛暑の連続だ。
昨年の梅雨明けは23日、平年は19日であり、今年の夏到来は「ぶち早い」、そして「ぶち暑い」。
さて、「山口盆地の夏」といえば、恒例の夏祭りが思い浮かぶ。
そのトップを飾るのは、大内氏28代・教弘が1459(長禄3)年に京都から伝えて以来、550年もの伝統を持つ山口祇園祭。
20日(土)の御神幸、24日(水)の御中日祭、27日(土)の御還幸を中心に、さまざまな神事が繰り広げられる。
江戸時代初期には、15の鉾と4基の山が街を練り歩き、鷺の舞や祇園ばやしなど、その豪華絢爛な様は「西国一」と賞された。
地元はもとより近隣の村々、遠くは石見の国から押しかけるほどにぎわっていたという。
しかしながら、太平洋戦争中に中断。
戦後に再開されたものの、往時のにぎわいは取り戻せていない。
今年は、御輿が街を練り歩く初日と最終日が土曜日にあたるため、例年以上のにぎわいに期待したいところだ。
サンデー山口も、盛り上げに一役買おうと、18日(木)に「山口祇園祭特集号」を特別発行。
同日の新聞折込に加えて、20日には祭り会場にてスタッフが手配りします。
ぜひご覧ください。

↑ 昨年の御神幸直前の八坂神社の様子
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。